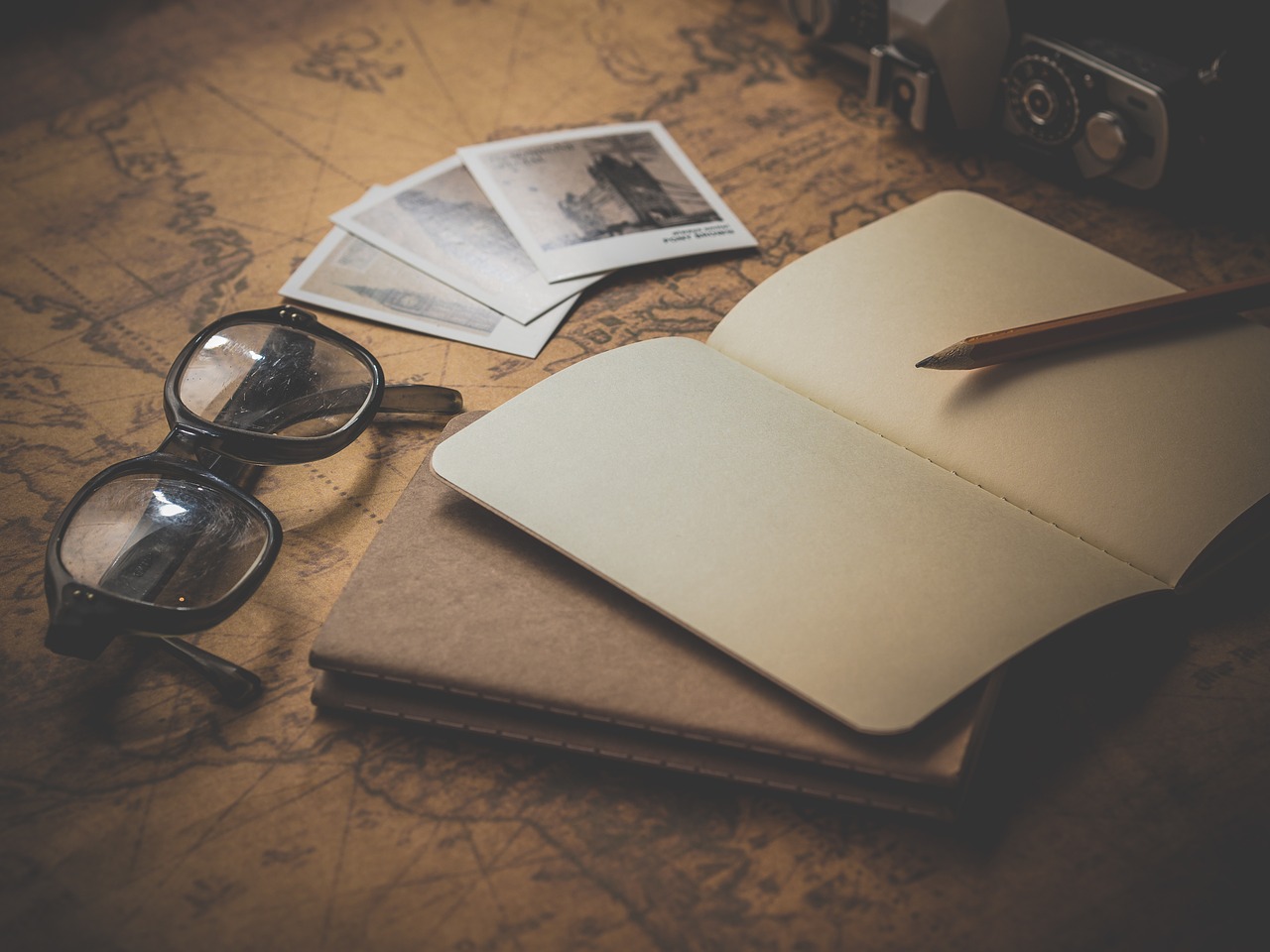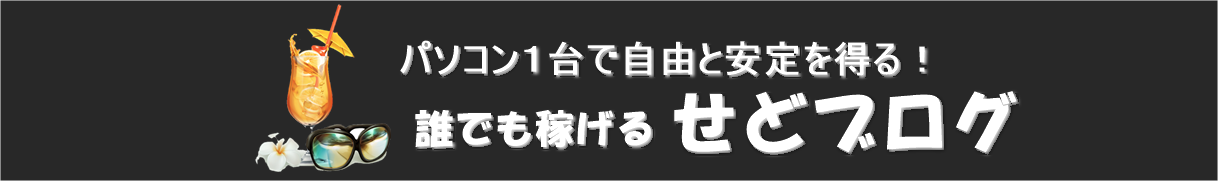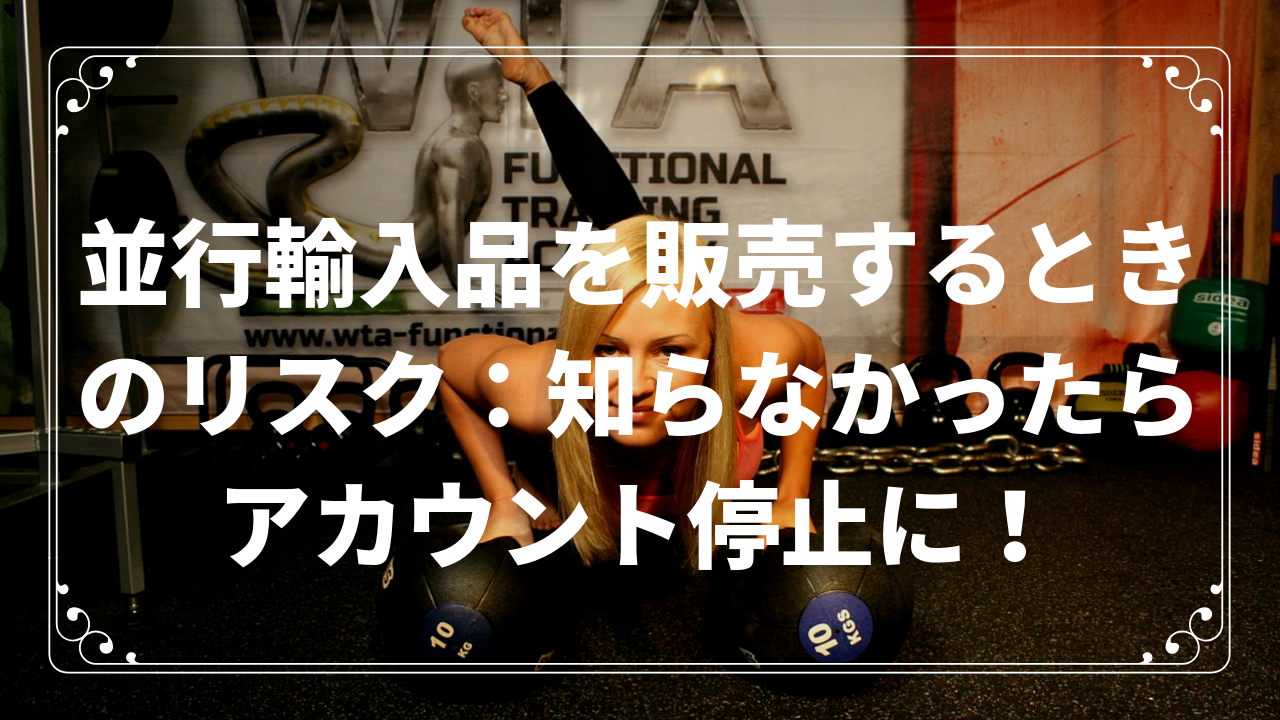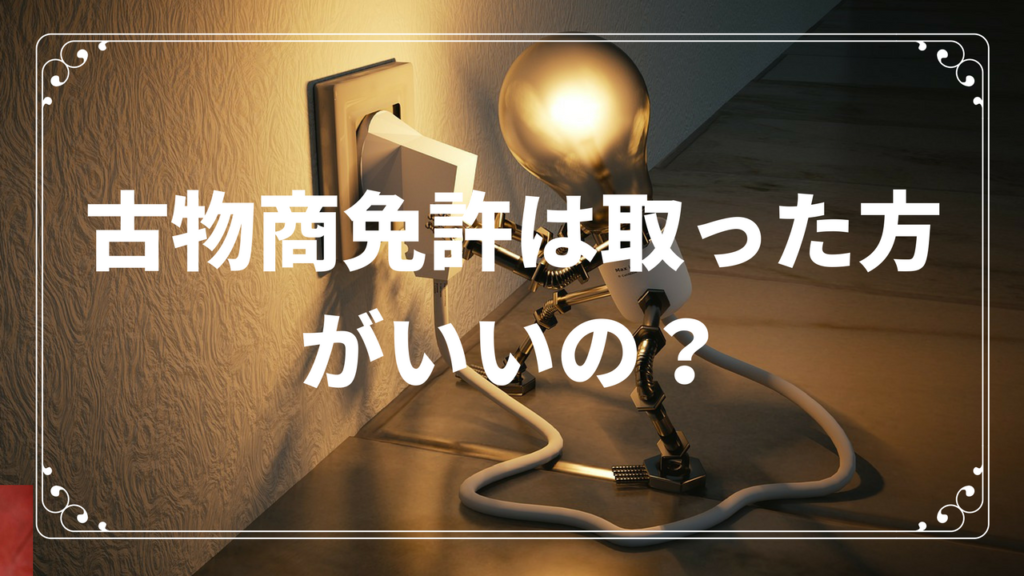
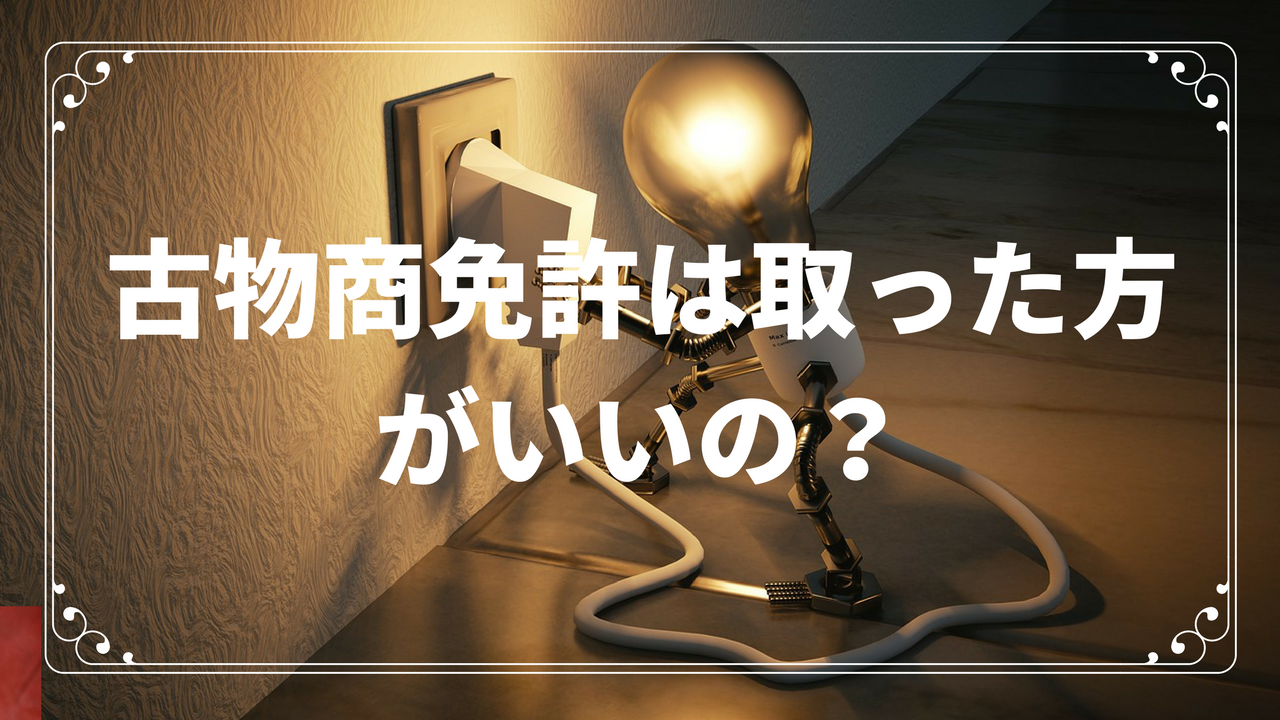
目次
古物商免許は取った方がいいの?
こんにちは。
今回は古物商許可証について解説してまいります。
そもそも古物商って何?必要なの?って思うかもしれません。
実店舗、無店舗のどちらでも古物(中古品)を取り扱う場合は、古物商許可証という免許が必要になります。
また古物商の免許をもってAmazonで販売すると、購入者から安心されて購買数が伸びる傾向もあるようです。
怪しい出品者ではないかと疑われたり、実際購入したものの商品が送られてこないショップとかもあり、評価数が少ないうちは特に中古品は売れずらいこともあります。
でもそういう場合に古物商の免許を持っていて、Amazonの出品者情報欄に古物商許可証が掲載されていると、安心して購入されていきます。
なぜならAmazonの出品者情報に記載できるので、購入者が確認できるからです。
本来は中古商品を購入してAmazonで販売する場合、古物商の許可証が必要となるのです。
あまり古物商免許を持っている方は少ないですが、あればお客様には安心感を与えます。
また先々Amazonが古物商の免許を持ったセラーでないと出品規制が入るといううわさも、聞くこともあります。
早いうちに持っておくといいと思いますが、今はAmazon販売で新品をメインに販売していればなくても大丈夫ですが、中古品も販売するのであれば古物商を持っていると販売数が伸びていきますし、信用度は違いますよね。
ネットオークションとかでも中古ビジネスは誰でも開業することが可能ですし、副業としても成り立つビジネスです。
特にインターネットでのオークションは人気で、法人・個人問わずに利用できることから古物商業者も多数参加しています。
中古ビジネスの仕入れ先として、中古市場やインターネットでの通販での仕入れ、フリーマーケットなどがあります。
古物市場とは古物商許可証を取得している人が利用できる市場です。
安く、安定した仕入れが出来るため、利用している古物商業者も少なくありません。
古物商許可証とは
そもそも古物商とは何なのかということなのですが、私が管轄の警察署の生活安全課で受けた説明は以下の通りです。
古物営業が許可制となっている理由
古物の売買は、その営業の性質上、盗難品や犯罪被害品が混ざっている事も多いようで、これを放置したままにすると、古物営業の市場が盗難品の流通の場となる恐れがあることからこれを防止するために許可制となったようです。ですので本来は許可なく販売はできないということです。
ですので場合によって、あなたが販売している商品が盗難品ではないかと疑われた場合、警察署が調査のため、立ち入り検査を行う場合もあるとのことでした。
ですが古物商の免許を持たずに販売している出品者も多くいます。
今のところ、この点に関しては警察は放置しています。ですが何かあった場合は処罰を受けるとのことでした。
例えば販売した中古品が実は盗難品であったりした場合に古物許可を取得しないまま、販売したことが発覚した場合です。
古物商とは、中古品を販売するために、その商品をどこかから購入して販売する行為です。
あなたの自宅の不用品を販売する場合は必要ではありません。
古物商許可証は繰り返し中古品の売買を繰り返す場合に必要となってきます。
そういう理由から中古品を売買するような場合、原則として古物商許可証を取得しなければなりません。(例外もあります)
古物商許可はどこで申請するのか?
古物商許可を受けるためには、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して許可申請をしなければなりません。
私も数年前に取得しました。申請してから、1カ月半ほどかかった覚えがあります。
古物商許可は各都道府県の公安委員会(東京都は警視庁)に対して申請をするということになっていますが、
実際に書類を提出するのは実は所轄(地域の警察署)の生活安全課に対して行います。

ところが、近くの警察署であればどこでもいいというわけではないのです。
警察には必ず「管轄」というものがありますので、それを必ず確認するようにしてください。
簡単な調べ方としては、あなたの最寄りの警察署に電話して聞くのが一番早いです。
そこへ電話をかけて古物の営業を行う場所を伝えれば、管轄警察の住所・電話番号などを親切に教えてくれるはずです。
営業を行う場所とは電脳せどりなどで自宅で行う場合は自宅の住所が営業所とみなされます。
このとき注意すべきは、古物商の営業所の場所を管轄する警察を聞いて下さい。
住所地と営業所が違う場合はご注意下さい。管轄の確認が終わったら、まずは管轄の警察署へ電話予約をして出向きましょう。
警察署の生活安全課に伺うと申請に必要な用紙一式がもらえ、さらに担当の方が親切な方の場合は許可申請の方法を説明してくれます。あまり親切でない方の方が多いです。
私はえらくぶっきらぼうに対応されました。
申請用紙じたいはインターネットでダウンロードすることも可能なのですが、書類作成前に管轄警察へ直接伺うことをお勧めします。
というのも、古物商許可申請に必要な書類は実はケースバイケースで変わることが多いようです。
ただよく行政書士さんとかに頼まれる方もいますが、全然個人で十分取得できるので、あなたご自身で取得されるのをお勧めします。
余計な費用をかける必要はないと思います。それが終わったらいよいよ書類の取寄せです。
取寄せ書類にはだいたい以下のようなものがあります。
住民票 <1通300円前後> |
お住まいの市区町村で簡単に取得することができます。 必ず本籍地が記載されているものが必要となります。 |
| 市区町村発行の身分証明書 <1通300円~600円> |
「身分証明書」と言っても免許証や保険証のようなものではないです。 ご自身が「本籍地」を置いている市区町村で発行される証明書です。 本籍地が遠いような場合は、郵送などの手段を使って取寄せることになります。 |
| 登記されていないことの証明書 <1通300円> |
成年被後見人や被保佐人に該当しないことを証明する書類です。 各都道府県の法務局本局で申請しましょう。 ただ法務局本局は都道府県に1カ所しかありませんので、近くに本局がない場合は東京法務局後見登録課へ郵送請求することもできます。〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階 東京法務局民事行政部後見登録課 |
土地・建物の登記簿謄本 <土地600円 建物600円> |
古物商の営業所として使用する場所が、自分や親族の名義である場合に求められることが多いです。 |
| 登記事項証明書 (履歴事項全部証明書) <1通600円> |
法人(会社)で申請する場合には必ず必要です。 最寄の法務局で入手して下さい。 |
取寄せも全て終わりましたら、書類の作成に入りましょう。
| 古物商許可申請書 | |
| 5年間の略歴書 | |
| 欠格事由に該当しない誓約書 | |
| URL使用権限を疎明する資料 | ホームページを利用して古物の売買を行う場合 |
| 賃貸借契約書 | 営業所が賃貸の場合 |
| 使用承諾書 | 警察署の管轄によっては求められる |
| 中古車の保管場所証明資料 | 中古車を取り扱う場合 |
| 営業所在地図 | |
| など |
取寄せた書類を良く見て、間違えないように丁寧に書いて下さい。よくわからない場合は警察署がしっかり教えてはくれますのでしっかり準備していきましょう。
全ての書類が揃いましたら、必要部数を用意します。
必要部数は各都道府県によって違いますので、初めに警察署に行かれた時に確認されるといいでしょう。
全て2部必要というところもあります。
これも生活安全課に良く伺ってみてください。
しっかり準備したら、あとは警察署へ提出するだけです。
許可申請の審査料(19,000円分、警察署で収入印紙として購入する)を準備し、審査料は都道府県の証紙で支払いますが、警察署内で売っていることがほとんどです。
書類を提出しましたら、1カ月前後で許可の通知が来ます。
以下のような免許証が交付されます。
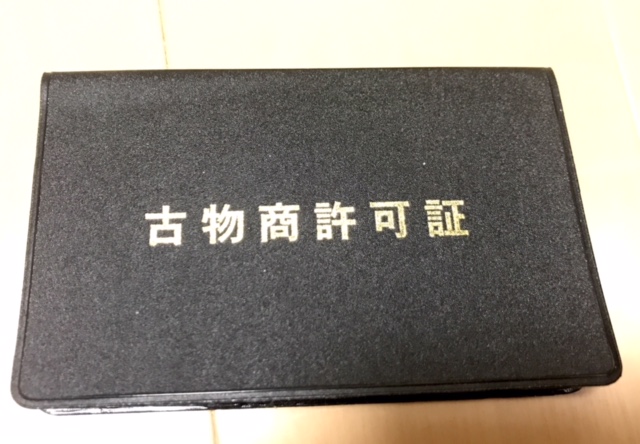
あなたが中古品で大きく利益を稼いでいきたいのであれば是非申請しておくことをお勧めいたします!
やってみたらわかりますが簡単に取得はできます。
是非チャレンジしてみてください♪